業務アプリ開発・運用代行
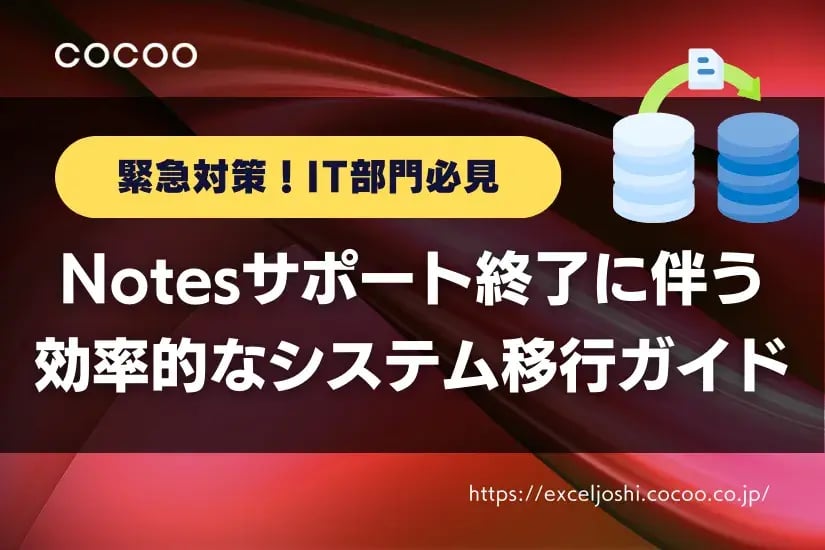
更新日:2025.04.16
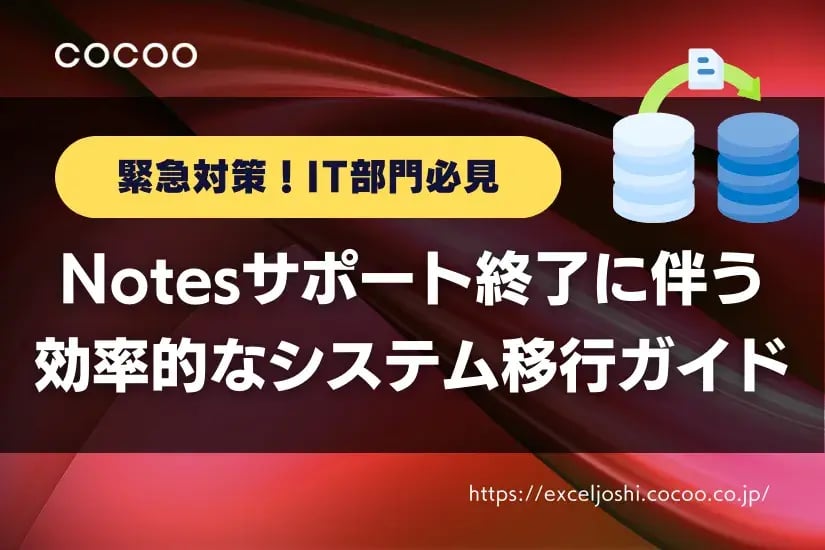
目次
1990年代から多くの大企業で活用されてきたグループウェア「Notes」は、現在HCL社が引き継いでいますが、サポートの終了が決定されました。その影響で、セキュリティ面でのリスクや業務効率の低下が懸念されており、今まさに迅速な対応が求められています。
本ガイドでは、スムーズな移行を実現するための効果的な手順や最新のベストプラクティスをわかりやすくご案内。限られたリソースの中でもリスクを最小限に抑え、安心して移行を進めていただくための具体的な戦略をご紹介します。

HCL社が提供するグループウェア「Notes/Domino」は、2024年から2025年にかけて一部バージョンのサポート終了が発表されています。
この背景には、クラウドの普及やセキュリティ要件の高度化など、グループウェアを取り巻く環境の変化があります。そのため、企業はできるだけ早く、今後の対応を検討する必要があります。
Notesのサポートが終わると、セキュリティパッチや技術サポートが受けられなくなり、システムが脆弱な状態になります。その結果、以下のようなリスクが発生します。
特に「セキュリティリスクの高まり」と「業務の非効率化」は、企業活動に直結する重大な問題です。
古いシステムでは、新しいツールや働き方に対応できず、従業員の生産性が下がったり、他社との競争力に差が出たりする恐れもあります。
だからこそ、Notesを使い続けている企業には、「何から移行するか」だけでなく、「どう業務を見直していくか」も含めた総合的な判断と、スピーディな対応が求められているのです。
HCL Notesのサポート終了に伴い、各バージョンごとのサポート終了時期が明確になっています。Domino v9.0.x、v10.0.x、v11.0.xのサポートは、2024年から2025年にかけて順次終了する予定です。
これにより、企業は自社の利用しているバージョンがサポート対象外となる前に、適切な対応を検討する必要があります。
最新バージョンのv14は、2023年12月7日にリリースされ、メール、カレンダー、セキュリティ機能などが大幅に改善されています。HCLSoftwareは現在もNotes/Dominoの開発とサポートを継続しており、最新バージョンの利用を推奨しています。
自社のシステムがサポート終了の対象となるかを確認するためには、現在使用しているNotes/Dominoのバージョンを特定する必要があります。バージョン情報は、Notesクライアントの「ヘルプ」メニューから「バージョン情報」を選択することで確認できます。
Notesのサポート終了は、企業のITシステムや日々の業務の流れに大きな影響を与えます。サポートが終わることで、セキュリティの不安が増したり、普段通りの業務が続けられなくなるリスクが高まるほか、古いシステムを使い続けるためのコストもどんどん膨らんでしまいます。
サポート終了と同時に新しい脆弱性への対策パッチ(修正プログラム)が提供されなくなります。
この状態で使い続けると、サイバー攻撃を受けやすくなり、大切な顧客情報や業務データが漏えいしたり、システムが止まってしまうといった深刻な問題が起きるかもしれません。
また、古いNotesの環境を維持し続けるには、専門知識を持った人材の確保や、時代に合わないシステムとの付き合いが必要になります。
新しいソフトやパソコンとの相性(互換性)が悪く、思い通りに動かなくなったり、業務を進める上で無駄な調整作業が発生することもあるでしょう。
こうした問題は、現場だけでなく経営レベルの意思決定やIT戦略にも影響を与えます。
だからこそ、「今のうちにどんなシステムにどう移行するか」を計画し、将来を見据えた準備を進めることがとても大切です。

情報システム・IT事務代行サービス

システム移行を成功させるためには、機能要件、コスト、サポート体制など、さまざまな選定基準を慎重に検討する必要があります。また、クラウドサービスやオンプレミスソリューションなど、移行先のオプションも多岐にわたります。
企業のニーズに最適な移行先を選ぶためのポイントと、各オプションの特徴や利点について、以下で詳しく解説します。
移行先のシステムを選定する際には、主要機能の確認とサポート体制の評価が不可欠です。
まず、情報共有やタスク管理、セキュリティ機能など、業務に必要な機能が充実しているかを詳細に検討します。次に、技術サポートの提供形態、対応時間、トレーニングの有無など、サポート体制が充実しているかを確認します。
最後に、自社の運用ニーズに合致しているかを評価するためのチェックポイントを以下に示します。
システム移行を成功させるためには、信頼性の高い移行ツールやサービスの選定が不可欠です。現在市場には多くの移行ツールやサービスが提供されており、それぞれが異なる特徴や利点を持っています。
ここでは、特に高く評価されている移行ツールとサービスを紹介し、各々の機能や導入事例を比較します。
例えば、Microsoft Azure Migrateは、クラウドへの移行を支援する包括的なツールであり、自動化された評価機能やコスト分析が特徴です。CloudEndure Migrationは、高速かつ信頼性の高いレプリケーション機能を提供し、ダウンタイムを最小限に抑えつつ移行を実現します。
また、IBM Cloud Migration Servicesは、専門家によるサポートを提供し、複雑な移行プロジェクトをスムーズに進行させることが可能です。
以下が、移行ツールやサービスを選択する際に考慮すべき基準です。
これらの基準を基に、自社に最適な移行ツールやサービスを選定することで、効率的かつ安全なシステム移行を実現できます。
システム移行において、クラウドベースのソリューションとオンプレミスの選択は重要な決断です。各選択肢にはそれぞれメリットとデメリットがあり、自社のニーズや予算、将来的な拡張性を考慮する必要があります。
以下の観点から両者を比較検討しましょう。
これらの要素を総合的に評価し、自社のIT戦略や業務要件に最適な選択肢を見つけることが重要です。


効率的な移行プロセスを実現するためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。本ガイドでは、システム移行全体の流れを視覚的に理解し、各ステップの概要と重要なポイントを紹介します。
これにより、スムーズでリスクの少ない移行作業をサポートし、読者が計画的にプロジェクトを進められるよう支援します。次のセクションでは、具体的な手順やベストプラクティスを詳しく解説します。
移行計画の立案と準備は、システム移行の成功を左右する重要なステップです。明確な目標設定やタイムラインの策定、リソースの適切な配分を行うことで、効率的かつ効果的な移行プロセスを構築します。
また、現状のシステム環境の詳細な分析やリスク評価を通じて、潜在的な課題を事前に把握し、スムーズな移行を実現するための基盤を整えます。
現状の利用環境の分析・調査は、システム移行を成功させるための第一歩です。まず、現行のNotesシステムの使用状況や依存関係を把握することが重要です。
これには、ユーザーへのアンケート調査やシステムログのレビュー、既存の統合ポイントのマッピングなどの方法があります。これにより、システム全体の構造や主要な機能、外部システムとの連携状況を明確に把握できます。
次に、移行に必要な情報として、データ量、ユーザー数、カスタマイズ内容を詳細に収集する手順を踏みます。具体的には、データベースのサイズや成長率の評価、アクティブなユーザー数の把握、カスタマイズされた機能やスクリプトのリストアップなどが含まれます。
この情報は、移行先のシステム選定や移行方法の決定において欠かせない要素となります。
最後に、分析結果を基に移行戦略を策定する際には、収集したデータを活用して優先順位やリソース配分を決定します。例えば、重要度の高い機能から順に移行を進める段階的なアプローチや、データ移行の自動化ツールを導入することで効率化を図る方法などがあります。
また、リスク評価を行い、潜在的な問題点に対する対策を事前に講じることも重要です。
システム移行を成功させるためには、効果的な移行プロジェクトチームの組成が欠かせません。適切なメンバーを配置し、チーム内のコミュニケーションや協力体制を確立することで、スムーズな移行プロセスを実現できます。
チームメンバーの役割には以下のようなものがあります。
コミュニケーションと協力体制を構築するためには、定期的なミーティングの開催や情報共有ツールの活用が重要です。これにより、メンバー間の連携が強化され、問題発生時にも迅速に対応できます。
さらに、チームビルディングを重視することで、メンバー間の信頼関係が築かれ、プロジェクト全体の士気と効率が向上します。共同作業を通じて協力体制を強化し、移行プロジェクトの成功に導くことが可能となります。
データ移行は、システム更新やプラットフォーム変更時において極めて重要なプロセスです。効率的かつ安全にデータを新しい環境へ転送することで、業務の中断を最小限に抑え、継続的な業務運営を支える基盤となります。
まずはデータ移行全体の流れを理解し、次に具体的な移行方法や使用するツールについて把握し、最後に移行中に発生し得る問題点とその対処法を確認することが成功への鍵となります。
データ移行プロセスは主に以下のステップで構成されます。
具体的な移行方法としては、CSVファイルのインポートが一般的です。CSV形式は多くのシステムでサポートされており、データの抽出や変換が比較的容易に行えます。移行ツールとしては、HCL Softwareが提供する最新バージョンのNotes/Dominoに対応した専用ツールや、サードパーティ製のデータ移行ソフトウェアが利用可能です。
これらの問題を未然に防ぐためには、事前の徹底したデータ分析とテスト移行の実施が重要です。また、移行プロセス中は定期的なバックアップを取得し、万一のトラブル発生時には迅速に復旧できる体制を整えることが求められます。
さらに、移行後のデータ検証を行い、新システム上でのデータの正確性と完全性を確認することが不可欠です。ユーザーからのフィードバックを収集し、必要に応じて調整を行うことで、移行後の業務運用を円滑に開始することができます。
効率的なデータ移行を実現するためには、計画的なアプローチと適切なツールの選定、そして柔軟な問題解決能力が求められます。これらを踏まえて準備を進めることで、システム移行の成功と業務の継続性を確保することが可能となります。

情報システム・IT事務代行サービス
CSVファイルのインポート機能を利用することで、効率的かつ正確にデータを新しいシステムに移行することが可能です。以下では、移行元のNotesからデータをCSV形式でエクスポートする手順と、移行先のシステムへのインポート方法について詳しく解説します。
移行元のNotesからデータをCSV形式でエクスポートする手順
移行先のシステムへのCSVファイルインポートの方法
データ整合性を保つための注意点やベストプラクティス
これらの手順と注意点を遵守することで、スムーズかつ安全なデータ移行を実現し、業務の継続性を確保することができます。
システム移行においてデータのバックアップと検証は、成功の鍵を握る重要なプロセスです。これらのステップを確実に実施することで、データの損失や不整合を防ぎ、スムーズな移行を実現します。
1. 移行前に必要なデータバックアップの方法と重要性
データバックアップは、移行作業が開始される前に実施する必要があります。以下の方法とその重要性について説明します。
これらの方法を用いることで、移行中に予期せぬデータ損失が発生した場合でも、迅速に復旧することが可能となります。
2. バックアップデータの検証手順を具体的に述べ、データ損失を防ぐ方法を紹介します
バックアップデータの検証は、バックアップが正常に完了し、データが正確に保存されていることを確認するために不可欠です。以下の手順を参考にしてください。
これらの手順を踏むことで、バックアップデータの信頼性を高め、移行作業中のデータ損失リスクを大幅に低減できます。
3. 移行後にデータの完全性と正確性を確認するための検証方法を提供します
システム移行が完了した後、データの完全性と正確性を確認するための検証が必要です。以下の方法を活用してください。
これらの検証方法を実施することで、移行後のデータが完全で正確であることを保証し、業務の継続性を確保します。
システム移行後のスムーズな運用を確保するためには、テストプロセスの徹底とユーザーへの適切なトレーニングが不可欠です。
本セクションでは、移行先システムの機能確認方法や、実際の使用環境に合わせたテストケースの作成、そしてユーザーが新しいシステムを効果的に活用できるようにするためのトレーニングプログラムやサポート体制の構築について概要を紹介します。
移行先システムの機能テストは、システム移行プロジェクトの成功に欠かせない重要なステップです。テスト計画の立案、実際の運用シナリオに基づいた機能テストの実施、そしてテスト結果の評価とフィードバックの取り扱いを適切に行うことで、新システムが業務要件を満たし、スムーズに運用開始できることを確認します。
テスト計画の立案方法とテスト項目の設定 効果的なテスト計画を策定するためには、まず移行先システムで必要とされる機能要件を明確にします。具体的な業務フローやユーザーのニーズを基に、テスト項目を設定し、各項目に対する期待される結果を定義します。
また、テストの優先順位を決定し、リソースや時間を効率的に配分するためのスケジュールを作成します。
実際の運用シナリオを基にした機能テストの実施方法 移行先システムが実際の業務環境でどのように機能するかを確認するために、現実的な運用シナリオを用いてテストを行います。ユーザーが日常的に使用する機能や、特定の業務プロセスにおける操作をシミュレーションし、システムの応答やパフォーマンスを評価します。
これにより、潜在的な問題点を早期に発見し、改善することが可能となります。
テストの結果を客観的に評価するための基準を事前に設定します。具体的には、システムの安定性、機能の正確性、ユーザーインターフェースの使いやすさなど、多角的な視点から評価します。
評価結果に基づいて、必要な修正や調整を行い、継続的に改善を図るためのフィードバックループを確立します。ユーザーからの意見や提案も積極的に取り入れることで、移行後のシステムがより実用的で満足度の高いものとなります。
システム移行後、ユーザーが新しい環境に迅速かつ効果的に適応できるよう、包括的なトレーニングプログラムの設計が不可欠です。
これには、実践的なハンズオンセッションや詳細なマニュアルの提供が含まれ、ユーザーの理解を深めるとともに、業務のスムーズな継続を支援します。
さらに、移行後には効率的なサポート体制の構築が求められます。具体的には、ヘルプデスクの設置やFAQの整備、継続的な教育プログラムの導入などがあり、ユーザーが直面する課題に迅速に対応できる環境を提供します。
最後に、ユーザーからのフィードバックを積極的に活用し、トレーニングやサポートの質を継続的に改善することが重要です。これにより、ユーザーの満足度を高め、新しいシステムの定着を促進します。

料金のご案内

システム移行が完了した後の管理およびサポート体制の確立は、企業の運用効率と継続的な業務改善にとって非常に重要です。
このセクションでは、移行後のシステム運用の効率化方法や、サポート終了製品のアップデートとバージョン管理の重要性、さらには継続的なサポート体制と将来的なシステム更新への対応策について詳しく解説します。
移行後のシステムの運用効率化は、システム移行を成功させるための重要なステップです。新しい環境でのスムーズな運用を実現するためには、適切なツールやプロセスの導入が不可欠となります。
運用を最適化するためのツールやプロセスとしては、IT自動化ツールや統合管理ソリューションの導入が挙げられます。これらのツールを活用することで、日常的な運用作業の自動化やリソースの効率的な配分が可能となり、手動作業の負担を軽減します。
また、標準化されたプロセスを確立することで、運用の一貫性と品質を維持することができます。
パフォーマンス監視やリソース管理のベストプラクティスには、リアルタイムでのシステム監視や定期的なパフォーマンス評価が含まれます。これにより、潜在的な問題を早期に検出し、迅速な対応が可能となります。
また、リソースの適切な管理を行うことで、システムの安定性を確保し、無駄なコストを削減することができます。
運用効率化によるコスト削減や生産性向上の具体的な事例として、ある中小企業では自動化ツールの導入により、年間で約30%の運用コストを削減しました。
また、業務プロセスの最適化により、従業員一人当たりの生産性が20%向上し、全体的な業務効率が大幅に改善されました。これらの成果は、適切なツールとプロセスの導入がもたらす具体的なメリットを示しています。
サポート終了製品のアップデートとバージョン管理は、システムの安全性と効率性を維持するために不可欠なプロセスです。
サポートが終了する前に適切なアップデートやパッチを適用することで、セキュリティリスクを最小限に抑え、業務の継続性を確保することが可能です。
まず、重要なアップデートやパッチの適用方法について解説します。サポート終了前には、最新のセキュリティパッチやバグフィックスを迅速に適用することが求められます。
HCLが提供するアップデートガイドラインに従い、定期的なシステムチェックとアップデートのスケジュールを策定することが重要です。
また、適用するパッチの互換性や影響範囲を事前に検証することで、予期せぬシステム障害を防ぐことができます。
バージョン管理の基本概念とその実践方法も重要な要素です。バージョン管理とは、ソフトウェアの各バージョンの変更履歴を追跡し、必要に応じて特定のバージョンに戻すことを可能にするプロセスです。
これにより、システムの安定性を保ちつつ新機能の導入や改善を行うことができます。効果的なバージョン管理には、適切なドキュメント化や変更管理の徹底が求められます。
最後に、更新プロセスをスムーズに行うためのツールやガイドラインの活用が推奨されます。自動化ツールを使用することで、アップデート作業の効率化とヒューマンエラーの削減が可能です。
また、明確なガイドラインを設定し、チーム全体で共有することで、一貫した更新手順を維持し、システムの安全性と最新性を確実に保つことができます。
これらの対策により、サポート終了後も安定したシステム運用が実現できます。

現在利用中のNotes/Dominoがv9.0.x〜v11.0.xである場合、2024年から2025年にかけて順次サポートが終了します。
セキュリティパッチの提供停止や技術支援の終了により、業務リスクが高まる前に早急な対応が求められます。
まずは自社の利用バージョンと終了時期を把握し、移行スケジュールの策定を進めましょう。
システム移行は、ツールの入れ替えだけに留まりません。実は、業務フローや情報共有のあり方を見直す絶好のタイミングです。
「属人化されたExcel管理」「アナログな承認フロー」「多重入力の非効率さ」など、これまで見過ごされてきた課題に目を向け、移行を“業務改革のきっかけ”に変えることができます。
Notes移行後、「とりあえずExcelで処理している業務が増えてしまった」という企業も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、コクー株式会社の「EXCEL女子」サービスです。
EXCEL女子は、ノーコードツール「CELF」を活用し、Excel業務の“見える化”と“仕組み化”を支援。
IT部門の負担を増やさず、現場業務をスマートに改善する伴走型サービスです。
業務改善は、移行のその先にある“成果”です。
システム移行と並行して、業務のあり方そのものも再設計してみませんか?
CELFは30日間無料プランを利用できますので、この機会に社内業務の効率化・自動化を実現してみませんか?
